のぼりです
【呼吸】
『光陰矢の如し』という言葉を習ったのは何年生の時だったのだろうか。
月日が経つのは早いもの、という意味も「歳を取ると過ぎ去りし時間のうつろいは
誠に早く思えるもので、今目前の課題に苦しむ若人よ、逃げる事なくゆっくりでも
しっかり歩き続けなさい。」
今の自分の年齢で解釈すればこの様な内容の説明を受けたはずだが、子どもなりに
心に残る言葉であった。
当時小学生の自分には想像も及ばぬ何十年先の自分等、どう転んでも思い描きよう
もないが、「人生とは光と陰、の展開がまるで矢のように感じるのだ」と言うその
スピード感と、自分や人の内面には誰しも「光と陰」が存在すると言う言葉に、鮮
烈な印象を持った。
光と陰、成長の先には何やらカッコ良くも未知の得体の知れぬ感情が誰にでもある。
すると当時は小さなコミュニティであっても、結構仲間外れにされたり、意味もわ
からず教師に殴られたり、苛めていた奴がそいつの家の裏でシクシク泣いているの
を見たり、訳もわからぬままにそれなりに必死に毎日を送っていた身には、理不尽
とも苦衷とも思える事は、「光と陰」の中に収まるのだと、少し安心した記憶はし
っかりあった。
意味のわからない訳のわからない事は、とても怖い要素を含んでいるのはこの年齢
になってもよくわかるから、何かしらの括りの知識を得たのは子どもながらホッと
したのだろう。
今こうして、『光陰矢の如し』をまさに体感している時、振り返る事の多さに改め
て驚きと、その時々の必死さや未熟さを思いながらも、所詮は過去話としてその気
分は未だ片隅に追いやる。
この矢はまだまだ健在のようで、止まることも偲ぶ事も許してはくれず、日々の緊
張と真剣さを求めて離さない。
『光と陰』その心に常に住み続ける要素は、互いの存在を意識し合いながら、いや
常に一つの組合わせとして構成されながら、私の日常に有っては時に物事の判断の
鍵となったり、自信の程を打ち壊すほどの鋭さや厳しさもあり、その交互に出現す
る様が、感情や感想として言葉や態度に現れたりもする。
『光陰』の存在があるとすれば、よく唱える『陰陽の世界』『プラスマイナス』の
世界の話しの骨子と、全く変わらない事を教えてくれる。
違いとすれば『矢』があるかないかで、『矢の如く飛び行く』事で時間軸を理解さ
せ、人生の長き時間も振り返る頃には、誠に短いものぞと言えるよと教える。そし
て、光と陰の幅に時間の長さを加えると立体的にその人生が浮かび上がる。
すると『陰陽』の言葉にその事と当てはまるのは『陰陽道』と言う呼称の世界か。
道は時間の移ろいをも現すと解釈できるから、まさに人生とは『陰陽』の世界に則
りひたすら歩く世界、とでも言える。
残念ながら『陰陽道』そのものは学識も全く持たないから語れぬが、おそらく進行
形の状態より求め活かす世界であり、『光陰矢の如し』は、過去たるものを有して
のち初めて理解する世界と言えるだろう。
では『プラスマイナス』の世界は、との疑問には『プラスマイナス』の世界の時間
に当てはまる要素は、統計として観ると『加減』によって根拠と出来るから、『プ
ラスマイナス』でその人生の収支は、ここまでの納得感は、と表してもいい。
こうして考えると、人生は常にでんでん太鼓のように、光と陰、陰と陽、プラスと
マイナスなど、真反対の心持ちや要素を交互に用いて成り立つものだとも解釈出来
る。
光光光とならず陰陰陰ともなり得ず、何かしらの均等性を有しながら、実はその事
が最重要な事とその本能は知って『人』として、存在させてもらっているのかも知
れない。
いつの世も『これがそれがあれが絶対』と呼べるものはなく、ただひたすらに『吸
っては吐く』この呼吸のリズムを基本にしてこそその存在はあるのだとよくわかる。
億人の世界には億人分の個性があり、億の考え方があるはずで意識して身構えてあ
らゆる現象に人が集中すると、必ずやそこに有る真反対の要素を理解してこそ、人
は進み解きほぐされていくものだと思います。
誰であっても人の原点はその呼吸とともに社会に飛び出しては、その成長の難しさ
を『光陰』と捉え『陰陽』と理解し『プラスマイナス』と表しながら脈々と営み続
けていくものなのでしょう。
時に高揚も落ち込みもまた繰り返しながら、果たしてこの先どこまで頑張れるもの
か、歩き続けられるものかは定かではないけれども、思い出してはしっかり『吸っ
ては吐いて』参ろうと思います。
店舗情報

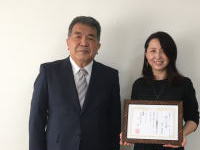
初級科修了式・髙尾さん

初級科修了式・宇野さん

初級科修了式・宇野さん
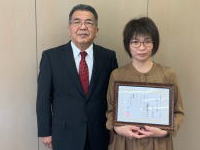
初級科修了式・佐野さん、

初級科修了式・佐野さん

特別講座

特別講座

特別講座

特別講座

特別講座